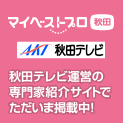2025年
10月
29日
水
日経平均株価、5万1000円台へ! そんな今こそ知るべき「光と影」
こんにちは。
秋田のファイナンシャルプランナー、土田茂です。
連日、ニュースで株価の話題が取り上げられていますね。
29日の日経平均株価は、ついに5万1300円台となり、過去最高値を更新しました。
資産形成層の方もですが、50代、60代で退職金の受け取りが見えてきた方にとっても「投資」は気になるキーワードです。
しかし、これだけニュースが盛り上がっていると、
「今さら始めても大丈夫?」
「もしかして、一番高い時に買ってしまうのでは…」
と、期待よりも不安が大きくなってしまう方も多いのではないでしょうか。
「老後の生活費は、本当に年金だけで足りるだろうか…」
「インフレ(物価上昇)で、貯金の価値が目減りしたらどうしよう…」
そんな漠然とした不安を抱えながら、この景気の良いニュースをどう受け止めたらよいか。 今日は、この「株価最高値」のニュースに隠された、私たちの将来に関わる「明るい面(光)」と「知っておくべき面(影)」を、わかりやすく解説します。
明るい面(光):なぜ今、日本の株が買われているのか?
まず、なぜこんなに株価が上がっているのでしょうか?
難しい経済用語は抜きにして、ポイントを掴みましょう。
-
アメリカ経済が絶好調 ニュースにもありましたが、アメリカの主要な株価(ダウ平均)も最高値を更新中です。特にAI(人工知能)関連の企業がぐんぐん伸びており、その勢いが世界中に広がっています。
-
海外の投資家が「日本株」に注目している 実は、今の日本株ブームを牽引しているのは、私たち日本人投資家というより、「海外の投資家」です。彼らが「これからの日本企業は伸びそうだ」と期待して、日本の会社の株をたくさん買っているのです。
-
日本の企業も頑張っている 特にAI(人工知能)の分野で使われる機械(半導体テスター)を作っているアドバンテストのような会社が、業績予想を大きく伸ばしています。日米政府の後押しもあり、日立製作所やソフトバンクグループなど、世界で活躍する日本の大企業も注目されています。
景気が良く、企業が儲かれば、回り回って私たちの生活や雇用にも良い影響が期待できます。
これは素直に「明るいニュース」と言えますね。
知っておくべき面(影):手放しで喜べない「2つの理由」
しかし、このニュース、良いことばかりでしょうか?
「資産運用する」私たちにとって、冷静に見るべきポイントが2つあります。
1. 「円安(えんやす)」が隠れている
記事の中に、少し難しいですが大切なことが書かれていました。
「日経平均の年初来の上昇率は28日時点で26%に対し、日経平均を米ドルで換算したドル建て日経平均は31%だ」
これはどういう意味でしょうか? 簡単に言えば、「円の価値が下がっている(円安)」ということです。
海外の投資家(例えばアメリカ人)から見ると、日本株は「株価の上昇」と「円安(安く買える)」のダブルでお得に見えています。だから、たくさん買ってくれるのです。
しかし、私たち日本に住む者にとって、「円安」は輸入品(食料品、ガソリンなど)が値上がりすることを意味します。
つまり、
「株は上がっているけれど、同時に日々の生活費も上がっている(インフレ)」
という状態です。
2. 銀行預金の「価値」が減っている
ここで一番怖いのが、このインフレ(物価上昇)の状況下で、何もしないことです。
ニュースの最後にあるように、日銀(日本銀行)はまだ金融政策(金利)を変えそうにありません。 これはつまり、銀行の普通預金や定期預金の金利は、ほぼゼロのままだということです。
もし、物価が年に3%上がっているのに、銀行預金の金利が0.1%だとしたら…。
大切に貯めてきた退職金は、「金額」は変わらなくても、「買えるモノの量(=実質的な価値)」はどんどん減っていくことになります。
私たちは、どう行動すべきか?
このニュースから見えてくるのは、 「株価が最高値だから、今すぐ全額投資だ!」ということでも、 「怖いから、やっぱり全額銀行預金だ!」ということでもありません。
一番のリスクは、 「円安とインフレで『円』の価値が静かに減っていく現実」から目をそらし、大切な退職金を金利のつかない銀行に置いたままにしてしまうこと なのかもしれません。
株価が上がっているのは「光」ですが、同時にインフレという「影」も忍び寄っています。
「でも、投資は怖い」
「何から始めたらいいかわからない」
「誰に相談したらいいか…」
そのお気持ちは、痛いほどよくわかります。
私も知識が不足していたときはそうでした。
大切なのは、ご自身の退職金を「守る」部分と、インフレに負けないよう「育てる」部分に、きちんと仕分けすることです。それは、ご家族の状況や、ご自身の「安心できる範囲」によって、一人ひとり全く違います。
もし、ご自身の「漠然とした不安」の正体や、ご自身に合ったお金の置き場所を整理してみたいと思われましたら、ぜひ一度、お気軽にお声がけください。
まずはあなたのお話を伺いながら、一緒に「安心できる老後」への第一歩を考えるお手伝いをさせていただきます。
初回無料のご相談、こちらからお気軽にお問い合わせくださいね。
2025年
10月
24日
金
「大学さえ出れば安心」はもう古い?
こんにちは!
秋田のファイナンシャルプランナー土田茂です。
熊の出没が続いており、被害者も増えていますね。
土崎駅近辺にも出没していて散歩も怖くてできないような状況です。
猟友会員も減少しており、若い担い手もいない状況ですし、今後どうなっていくのでしょうか?
行政による具体的な施策がないと解決に向かわないですし本当に不安ですね。
さて、最近「生成AI(人工知能)」という言葉をテレビやネットで見ない日はないですよね。
少し前までは「遠い未来の話」のように感じていましたが、どうやら私たちの生活、特にお子さんたちの「働き方」に、もう影響が出始めているようです。
今日の日経新聞記事では、 AIがどんどん賢くなって、これまで人間がやっていた「知的労働」(いわいわゆるホワイトカラーのお仕事)を担うようになった結果、なんと「大学を卒業した人」の就職が難しくなっているというのです。
記事によると、アメリカでは今、配管工や大工さんといった「手に職をつける」ための職業訓練校への入学者が、前年から12%も増えているそうです。
その一方で、大学を卒業したばかりの20代前半の若者の失業率は9.2%まで上がっています。
これまでの常識では、「良い大学に入れば、将来安泰」というイメージがありましたよね。
でも、AIはプログラミングやコンサルティングなど、まさに大卒の人が得意としてきた分野の仕事も、どんどんできるようになっています。
その結果、今までは景気の影響を受けにくいとされてきた大卒の人たちが、就職で苦労するという「逆転現象」が起き始めているのです。
「でも、それはアメリカの話でしょ?」と思われるかもしれません。
しかし、「アメリカで起きたことは、数年遅れて日本でも起こる」とよく言われます。
記憶に新しいのが、2008年頃の「リーマンショック」です。
あのアメリカの大きな金融機関が倒産した時、日本は「直接の関係は少ない」と言われていました。
ところが、どうなったでしょう?
アメリカの不景気が世界に飛び火し、日本も得意な自動車や電化製品といった産業を中心に大きなダメージを受けました。
その結果、日本では「派遣切り」という言葉がニュースで毎日流れ、多くの人が職を失いました。
火元のアメリカとは違う形で、日本の経済が、非常に大きな打撃を受けたのです。
今回のAIによる「大卒の就職難」というニュースも、決して対岸の火事ではありません。
私たち親にとって、子どもの将来は一番の心配事。
「高い学費を払って大学に行かせても、本当に子どもの将来のためになるのだろうか?」
…これからの時代はより一層将来を考えて進路を選ぶことが大切です。
そして、私たちに関わる年金の問題や介護・医療といった社会保障のこと、そしてAIの進化。
将来どうなるか本当に分からない不確実な時代だからこそ、「なんとなく成り行きで暮らす」のは一番怖い選択かもしれません。
未来が見えないからこそ、目をそらさず、家計や保険、将来のお金について
「計画を立てる(ライフプラン)」
ことが、私たち家族を守る一番の備えになるのだと思います。
今日もありがとうございました。
2025年
10月
21日
火
マイホームの購入予算、ざっくりとでも計算してみましょう!
こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの土田です。
将来のお金のこと、特に「マイホーム」は人生で一番大きなお買い物だけに、悩みますよね。
今回は、簡易的にではありますが、住宅購入の予算を検討する計算方法をお伝えします。
日本の中小企業のサラリーマンの平均生涯年収は約2億円程度と言われています。40年で均すと500万円です。※秋田の平均年収より高目ではありますが…。
そこで、こんなモデルケースで考えてみたいと思います。
【モデルケース】
-
夫:35歳(年収500万円)
-
妻:30歳(パート年収100万円)
-
お子さん:2人(3歳と1歳)
このご家族が、旦那さん(夫)が65歳で定年するまでの「30年間」で、どれくらい住宅にお金をかけられるか、一緒に「引き算」で考えてみましょう。
1. ご夫婦の「手取り」収入(30年分)は?
大切なのは、税金や社会保険料が引かれる前の「額面」ではなく、実際に使える「手取り」で考えることです。
-
旦那さん(年収500万円)の手取り 家族構成などにもよりますが、税金や社会保険料を引くと、手取りはざっくり「約390万円」ほどになります。 390万円 × 30年 = 1億1,700万円
-
奥様(年収100万円)の手取り パート年収100万円の場合、税金や社会保険料(夫の扶養内)はほぼかからないため、手取りは「約100万円」です。 100万円 × 30年 = 3,000万円
ご夫婦の30年間の手取り収入は、合計 1億4,700万円 となります。
※退職金がある場合は足してください。
2. これから「必ず出ていくお金」(30年分)は?
次に、この手取り収入から「必ず出ていくお金」を引いていきます。
-
お子さん2人の教育費 文部科学省の調査(令和3年度子供の学習費調査など)によると、幼稚園から大学まですべて公立(国公立)だとしても、1人あたり約1,000万円かかると言われています。 2人分で 約2,000万円
-
今の生活費(住宅費は除く) 仮に月15万円で生活しているとすると、30年分で… 15万円 × 12ヶ月 × 30年 = 5,400万円
-
その他の大きな支出 車の買い替え、車検、家電の買い替え、家族旅行、趣味など。仮に「年間100万円」は見ておくとすると、30年分で… 年間100万円 × 30年 = 3,000万円
支出合計は、2,000万 + 5,400万 + 3,000万 = 1億400万円 です。
3. 残ったお金は?
1億4,700万円(収入) - 1億400万円(支出) = 4,300万円
この「4,300万円」全額が、今回のモデルケースで住宅購入(頭金+ローン総額(金利分含む))に回せる金額でしょうか?
老後資金は(2000万円必要と言われてますね)?物価上昇は?増税されたら?
そもそも子供が大きくなったら生活費も増えるし…私立の大学や県外に進学したら…などなど。
そう考えると「4300万円」で住宅を購入するのは得策ではありません。
更に35歳で35年ローンを組んだら、支払いは70歳まで続きます。定年後も続くローンの支払いと、老後の生活資金と考えると不安しかありませんね。
とはいえ、実際にはこういった状況で住宅を購入している方が多くいらっしゃいます。
購入してからでは遅いので、こういった簡易的でも計算しておくことが大切です。
簡易的なものでなく
「うちの場合は、もっと具体的にどうなるの?」
「分かりやすく『見える化』して、安心したい」
「もし予算が厳しいなら、どう改善したらいいか知りたい」
そう思われた方は、ぜひ一度、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
ご家族が安心して暮らせる未来を、一緒に考えていきましょう。
今日もありがとうございました。
2025年
10月
17日
金
AIが俳優の仕事を奪う!?生涯現役で働くための作戦が必要な時代!
こんにちは!
秋田のファイナンシャルプランナー、土田茂です。
最近、テレビやネットで「AI(人工知能)」という言葉を耳にしない日はないくらい、私たちの生活に身近なものになってきましたね。
私も仕事で生成AIをよく活用していますが、本当に便利で賢く、進化のスピードも恐ろしいほど速いので、便利ではあるのですが、少し怖い感覚を持っています。
今日の日経新聞には、アメリカの映画の都ハリウッドで、AIをめぐって大きな騒動が起きているという記事がありました。
AIが作った架空の俳優、その名も「AI俳優」が登場し、本物の俳優さんたちが「私たちの仕事がなくなってしまう!」と、強い危機感を抱いているというのです。
ハリウッドの俳優さんたちの組合は、2023年に大規模なストライキを行いました。その大きな理由の一つが、このAIの問題だったそうです。
自分たちの演技や表情が、いつの間にかAIに学習されて、そっくりなCGキャラクターが作られてしまうかもしれない。そうなったら、自分たちの仕事はどうなるのか…。有名な俳優さんからも「もう私たちの仕事はおしまいだ」「本当に恐ろしい」といった声が上がるほど、深刻な問題になっています。
これは、ハリウッドという特別な世界の出来事だけではありません。他の記事には最先端のIT企業でさえ、「AIの進化が速すぎて、自分たちのサービスが時代遅れになってしまうかもしれない」と、強い危機感を抱いていることが報じられていました。
生き残るために、今までライバルだと思っていた会社と手を組むなど、必死の対応を迫られているのです。
ハリウッドスターや最先端の企業ですら、これほどの危機感を持っている。だとしたら、私たちの暮らしや仕事は、この先どうなっていくのでしょうか?
身近なところではスーパーのレジが自動になったり、飲食店の配膳をロボットが行っていたりする光景は、もはや珍しくありません。
私たちが普段している仕事、例えば事務作業や電話応対なども、AIの方が得意になる日が来るかもしれないのです。
「人生100年時代」と言われ、これからは70歳、75歳まで働くのが当たり前になるかもしれない、という話もよく聞きます。
でも、その時になって「AIやロボットに仕事が奪われてしまって、働きたくても働ける場所がない…」なんてことになったら、本当に困ってしまいますよね。
だからこそ、今から私たちも「自分自身のキャリア」について、真剣に考える必要があるのかもしれません。
例えば、新しい知識やスキルを学び直す「リスキリング」を始めたり、AIには真似のできない、人とのコミュニケーションや温かみが求められる仕事のスキルを、さらに磨いたりすることも大切になってくるでしょう。
そして、そうした具体的な行動を始める前に、もっと大切なことがあります。
それは、
「自分はこれから、どんな風に生きていきたいのか?」
という、ご自身の価値観と向き合う時間を持つことです。
「どんな働き方ができたら、幸せだと感じる?」
「何歳まで、どんな形で社会と関わっていたい?」
「家族と、どんな未来を築いていきたい?」
こうした「キャリアプラン」を考えることは、お金の計画を立てるのと同じくらい、いえ、それ以上に大切な「ライフプランニング」の一部です。
漠然とした未来への不安は、誰にでもあるものです。
でも、その不安をそのままにせず、ご自身の価値観を土台として「我が家のこれからの作戦」を考えてみる。
その一歩が、変化の激しい時代を乗り越えていくための、一番の力になるはずです。
もし、
「何から考えたらいいか分からない」
「家族とどんな風に話したらいいんだろう?」
と感じたら、ぜひ一度お話を聞かせてください。
一緒に頭の中を整理しながら、あなたとご家族にとっての「理想の未来地図」を描くお手伝いができれば嬉しく思います!
初回無料のご相談はこちらからどうぞ。
今日もありがとうございました。
2025年
10月
16日
木
なんだか不安…日本の順位がまた下がる?未来のために「我が家の作戦会議」を始めませんか?
こんにちは!
秋田のファイナンシャルプランナー、土田茂です。
連日の熊被害、今日は秋田市で建築中の家に熊が居座ったという事件が起こりました。
無事檻に掛かってくれたようですが、今年は熊被害が多いので、特に夜はあまり出歩かないなど気をつけましょう。
さて、今日の日経新聞に「2026年、日本の経済規模がインドに抜かれて世界5位になる見通し」という記事がありました。
少し前は世界第二位のGDPを誇っていた日本ですが、中国に抜かれ、ドイツにも抜かれたばかりなのに今度は世界最多の人口の国インドにも抜かれてしまうようです。
「GDP」なんて言われると少し難しく感じますが、これは「国が全体で稼ぐ力」のようなもの。
その日本の力が、世界の中で相対的に少しずつ小さくなっている、ということなんです。人口がぐんぐん増えて勢いのあるインドのような国に、追い抜かれていく。これが時代の大きな変化なんですね。
こんなニュースを見ると
「日本の将来、大丈夫かしら…」
「私たちの年金は?子どもたちの未来は?」
そんな漠然とした不安を感じてしまうのも、無理はありません。
国の大きな流れをすぐに変えることはできなくても、私たち自身の暮らしや家族の未来を守るために「今できること」は、きっとあるはずです。
時代の変化に取り残されないように、まずは「我が家」のことから見つめ直してみませんか?
その第一歩としておすすめしたいのが、家族の夢や将来の計画を話し合う「ライフプラン作り」です。
「子どもが大学に行く頃には、いくら必要?」
「私たちは、どんな風に年を重ねていきたい?」
「もしもの時、家族が困らないためには?」
こんな風に、家族のこれからを一枚の地図に描いてみるような作業です。
お金の計画はもちろんですが、何より大切なのは、ご自身やご家族が「どう生きたいか」を共有すること。
一人で、またご夫婦だけで悩んでいませんか?
もし「何から始めたらいいかわからない」と感じたら、ぜひ一度お話をお聞かせください。
まずは漠然とした不安を言葉にしてみるだけでも、きっと心が軽くなりますよ。
初回無料のご相談はこちらからどうぞ。
今日もありがとうございました。